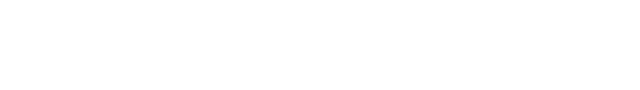生活習慣病
高血圧症
高血圧とは、血圧が135/85mmHg以上の状態が続くことを指します(家庭血圧では135/85mmHg、診察室では140/90mmHgが診断基準となることもあります)。
自覚症状がほとんどないことが多く、健康診断で偶然指摘されるケースが多いため、「サイレントキラー」と呼ばれています。
しかしながら、高血圧を放置していると、血管に常に負担がかかり、動脈硬化が進行しやすくなります。これにより、以下のような重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります:
-
心筋梗塞、狭心症などの虚血性心疾患
-
脳出血・脳梗塞などの脳血管疾患
-
心不全や不整脈
-
腎機能障害や慢性腎臓病(CKD)
-
大動脈瘤や末梢動脈疾患
これらは、ある日突然命に関わる事態を引き起こすこともあります。
当院では、循環器内科を専門とする立場から、「血圧の値」だけではなく、「血管や臓器への影響」までを見据えた高血圧診療を行っています。
心電図、心エコー、頸動脈エコーなどを用いて心臓や血管の状態を的確に評価し、一人ひとりに適した治療方針をご提案します。
治療は、まずは減塩・体重管理・運動・睡眠の改善などの生活習慣の見直しからスタートしますが、必要に応じて薬物療法も併用し、無理のない形で継続できる方法をご一緒に考えていきます。
健康診断で血圧が高いと指摘された方、ご家庭での血圧測定が気になる方は、「まだ大丈夫」と思わず、ぜひ早めにご相談ください。早期の対策が、将来の大きな病気の予防につながります。
糖尿病
糖尿病は、血液中の糖分(血糖)が慢性的に高い状態が続く病気です。インスリンというホルモンの分泌や働きに問題があるため、血糖がうまくコントロールできず、さまざまな合併症を引き起こすことがあります。
糖尿病には主に以下のタイプがあります:
1型糖尿病:インスリンがほとんど分泌されないタイプで、主に若年層に発症します。
2型糖尿病:インスリンの働きが悪くなる、または分泌量が減るタイプで、生活習慣や遺伝的要因が関与します。成人の糖尿病のほとんどがこのタイプです。
初期には自覚症状が少ないですが、進行すると次のような症状が現れることがあります:
- のどの渇き
- 頻尿
- 異常な疲労感
- 体重減少
放置すると、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こるリスクが高まり、心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気にもつながります。血液検査での血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)による診断が重要です。
治療と予防
治療の基本は、食事療法と運動療法を中心とした生活習慣の改善です。必要に応じてインスリン療法や血糖降下薬が使用されることがあります。適切な治療を続けることで、合併症のリスクを大幅に減らすことができます。
当クリニックでは、糖尿病の早期発見、適切な管理、そして合併症予防に力を入れており、定期的な検査と生活習慣の指導を行っています。患者一人ひとりに合った治療プランを提供し、健康な生活をサポートします。
糖尿病の診断・管理において、HbA1c(過去1~2か月の血糖状態を反映する指標)を迅速に測定できる機器を導入しています。採血から約3分で結果が出るため、その日の診察中に血糖コントロールの状況を把握し、すぐに方針を立てることができます。
―動脈硬化のリスクを日々診ている循環器内科としての視点から―
私は循環器内科を専門とし、これらの重篤な合併症と日々向き合ってきました。糖尿病によって引き起こされる心血管疾患を数多く診療してきた経験から、糖尿病の早期発見と厳格な管理が、将来の命を守ることにつながると強く感じています。
脂質異常症
脂質異常症は、動脈硬化のリスクを高め、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の発症に大きく関与しています。日本では、脂質異常症の早期発見と適切な治療が、長寿社会における重要な健康課題の一つとなっています。
日本動脈硬化学会の『動脈硬化性疾患予防ガイドライン』に基づき、脂質異常症の診断は以下のように定義されています:
LDL(悪玉)コレステロール:140 mg/dL以上
HDL(善玉)コレステロール:40 mg/dL未満
中性脂肪:150 mg/dL以上
これらの数値が持続的に基準を超える場合、脂質異常症と診断され、心血管リスクが高まるため、治療が必要です。
治療と予防
脂質異常症の治療は、食事療法や運動療法を中心とした生活習慣の改善が基本です。特に、LDLコレステロールが高い場合は、動物性脂肪の摂取を控え、野菜や魚を中心としたバランスの良い食生活が推奨されます。
それでも改善が見られない場合や、心血管疾患のリスクが高い場合には、薬物療法が必要となることがあります。コレステロール低下薬が処方され、血中の脂質バランスを整える治療が行われます。
日本では、食生活の欧米化により、脂質異常症の発症率が増加しています。特に、LDLコレステロールの高値が注目されており、成人の約4割が脂質異常症の傾向を持つとされています。また、日本人は欧米人に比べて、HDLコレステロールが高い一方で、LDLコレステロールの蓄積に対する耐性が弱いとされています。これは動脈硬化の進行が比較的早い要因の一つです。
脂質異常症は、自覚症状がほとんどなく、検診や血液検査で初めて発見されることが多い疾患です。したがって、定期的な健康チェックが非常に重要です。
当クリニックでは、皆さまの健康維持と動脈硬化予防および現時点での動脈硬化の評価のため、適切な検査と診断、生活習慣の指導を行い、必要に応じた薬物療法を提供いたします。
高尿酸血症・痛風
高尿酸血症は、血液中の尿酸値が高くなる状態を指し、これが進行すると痛風や腎臓病の原因となります。尿酸は体内の老廃物の一つで、通常は腎臓を通して排出されますが、体内で過剰に作られるか、排出がうまくいかないと尿酸値が上昇します。
症状
高尿酸血症そのものには自覚症状がほとんどありませんが、尿酸が結晶化し関節にたまると、痛風発作が起こり、関節の激しい痛みと炎症を引き起こします。特に足の親指に症状が出ることが多いです。また、尿酸が腎臓に蓄積すると、尿路結石や腎障害を引き起こすリスクがあります。
日本では生活習慣の変化により、高尿酸血症の発症率が増加しており、特に肥満や過度のアルコール摂取、食事の偏りがリスク要因とされています。
治療と予防
治療は生活習慣の改善が基本です。尿酸値を下げるためには、以下の点に気をつけることが重要です:
- バランスの良い食事(特にプリン体の多い食品を控える)
- アルコールの制限
- 十分な水分摂取
- 適度な運動
それでも尿酸値が高い場合は、薬物療法が必要になります。尿酸生成を抑制する薬や、尿酸の排出を促進する薬が処方されることがあります。
当クリニックでは、高尿酸血症や痛風の早期発見・治療に努めており、生活習慣のアドバイスや適切な治療を通じて、皆さまの健康維持をサポートいたします。