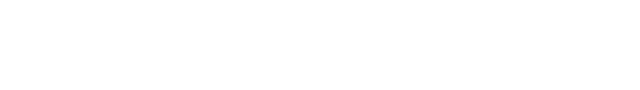循環器内科
心臓や血管に関連する疾患の診断・治療を専門とする診療科です。心臓病や血管病は、現代の生活習慣や加齢に伴い、増加傾向にあるため、早期発見と適切な治療が重要です。
心筋梗塞や狭心症、心不全、心房細動を代表する不整脈をはじめ、動脈硬化や閉塞性動脈硬化症といった血管の病気にも対応します。循環器内科医は、心臓の機能や構造に関する専門知識を持ち、胸部レントゲン、心電図、心臓超音波検査、脈波などの検査を駆使して正確な診断を行います。
加えて、循環器疾患は他の疾患とも関連が深いため、内科医としての総合的な視点からの診療が求められます。
神奈川区・港北区をはじめ横浜市内で循環器疾患にお悩みの方は、白楽駅徒歩5分の当院までご相談ください。
よくある疾患
高血圧症
血圧が持続的に正常値を超えて高い状態です。自覚症状がないことが多く、放置すると血管や内臓のダメージに伴い心筋梗塞や脳卒中、心不全、不整脈、腎臓病のリスクが高まります。
健康診断などで指摘された場合は放置せずご相談ください。
心不全
心不全とは、心臓が全身に十分な血液を送り出すことができなくなる状態を指します。疲れやすさ、息切れ、むくみなどが主な症状です。原因としては、高血圧や心筋梗塞、心臓弁膜症、不整脈、心筋症などが挙げられ、早期の診断と治療が重要です。薬物治療や生活習慣の改善、場合によっては手術が必要になることがあります。
狭心症
心臓に栄養を送る血管(冠動脈)が主に動脈硬化の進行で狭くなることで、心筋が十分な酸素を得られず、歩行時や運動時、階段や坂道を上るときの息切れや胸の痛み、胸の締め付けられるような症状が特徴的です。休むと数分から15分以内に症状が治まりますが、生活習慣の見直しのみでは治療が難しく、薬物療法やカテーテル治療(病態に応じて手術)が必要になることが多く専門医による緊急性の判断と適切な治療が必要となります。
当院では、循環器専門医の院長を中心に緊急性が高い場合には治療実績が豊富な総合病院へご紹介することもできます。
糖尿病に合併する場合は症状が出現しないこともあり、検診で心電図異常などを契機に診断されることもあります。
異型狭心症(冠攣縮性狭心症)
冠動脈が一時的に過度に収縮(攣縮:spasm)をきたすために著しく血流が低下し、心筋に酸素が供給されなくなることで狭心症のような症状が出現します。動脈硬化による狭心症と異なり、運動中ではなく安静時に生じやすく、おもに夜間から早朝に出現しやすい、喫煙後や飲酒した翌日などに出現する特徴があります。
正確に診断することが難しい疾患で、心筋梗塞や突然死の原因なりますが、薬物療法で発作をほぼ予防できるために循環器専門医による診察が必要です。
心筋梗塞
心筋梗塞は血栓などが原因で冠動脈の血流が完全に途絶えるため、心筋が壊死を起こし、詰まった瞬間から安静時でも20分以上強い症状が続くことが狭心症と異なります。急速な息苦しさや冷や汗を伴うこともあり命にかかわる危険な状態に進行する疾患です。迅速な診断とカテーテル治療などが必要のために緊急で対応が可能な医療機関に紹介いたします。
心臓弁膜症
心臓弁膜症は、心臓にある4つの弁(僧帽弁、大動脈弁、三尖弁、肺動脈弁)のいずれかが正常に機能しなくなる病気です。心臓の弁は、血液が一方向に流れるように働いていますが、この弁が正しく開閉しないことで、血液の流れに異常が生じ、心臓に負担がかかります。
主な心臓弁膜症には、弁が狭くなる狭窄症と、弁が十分に閉じずに血液が逆流する閉鎖不全症があります。これにより、息切れ、むくみ、胸の痛み、動悸などの症状が現れることがありますが、初期段階では自覚症状がないこともあります。
心臓弁膜症は放置すると心不全の原因となり、命にかかわることもあるため、早期の診断と治療が必要です。当クリニックでは、心エコー検査などを用いた精密な検査を行い、重症の場合は手術が必要な場合もあるため、適切な専門医療機関への紹介も行っています。
不整脈
不整脈は、心臓の拍動が不規則になったり、通常よりも速く(頻脈)または遅く(徐脈)なる状態を指します。心臓は一定のリズムで血液を全身に送り出すポンプの役割を担っていますが、そのリズムが乱れると、血液循環に影響を与え、さまざまな症状や合併症を引き起こすことがあります。
主な不整脈の種類には、心房細動、上室性頻拍、洞不全症候群、房室ブロック、心室頻拍、心室細動、期外収縮などがあります。これらの不整脈は、動悸、息切れ、めまい、失神といった症状を引き起こす場合もありますが、無症状で進行することもあります。
不整脈は高血圧や心臓病などの基礎疾患に関連することが多く、放置すると脳梗塞や心不全などの重大な病気を引き起こすリスクがあります。当クリニックでは、心電図やホルター心電図(24時間心電図)などの検査を通じて不整脈を診断し、必要に応じて内服薬の治療や、専門施設への紹介も行っています。
心筋症
心筋症は、心臓の筋肉(心筋)が異常に肥大、硬化、または拡張する病気で、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなることがあります。心筋症にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因や症状が異なりますが、最も一般的なのは拡張型心筋症、肥大型心筋症、および拘束型心筋症です。
拡張型心筋症: 心臓の筋肉が弱まり、心室が拡張してポンプ機能が低下する病態です。原因にはウイルス感染、遺伝、過度のアルコール摂取などがあります。主な症状として、息切れやむくみ、疲れやすさが挙げられます。
肥大型心筋症: 心筋が異常に肥厚し、血液の流れが阻害されることがあります。特に遺伝的な要因が強いとされ、無症状で進行することもありますが、動悸や胸痛、場合によっては突然死を引き起こすこともあります。
拘束型心筋症: 心筋が硬化し、心臓が適切に拡張できなくなるタイプです。これは心臓の柔軟性が失われ、血液を十分に受け入れられなくなるため、心不全に至ることが多いです。
心筋症の診断には、心エコーや心電図、血液検査、MRIなどの精密検査が必要です。当クリニックでは、症状に合わせた適切な診断を行い、病態に応じた治療や、必要に応じて専門施設への紹介を行っています。心筋症は進行すると心不全や不整脈の原因になることがあるため、早期の発見と適切な管理が重要です。
閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症(PAD: Peripheral Artery Disease)は、主に脚の動脈が動脈硬化により狭くなり、血流が悪くなる疾患です。進行すると、歩行時に脚の痛みやしびれが生じ、さらに進行すると、安静時でも痛みを感じるようになります。重度の場合、血流不足により潰瘍や壊疽を引き起こすことがあります。
症状
初期段階では、歩行中に脚の筋肉に痛みや疲労を感じ、休むと改善するという「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が特徴的です。
進行すると、歩行距離が短くなり、安静時にも痛みを感じるようになります。
末期では、脚や足に潰瘍や壊疽が発生することがあります。
主な原因は、動脈硬化です。動脈硬化は高血圧、糖尿病、喫煙、脂質異常症などのリスク要因により進行します。これらのリスクをコントロールすることが、閉塞性動脈硬化症の予防につながります。
当クリニックでは、血流の評価を行うためのABI検査(足関節上腕血圧比検査)などを実施し、早期診断を目指しています。治療としては、生活習慣の改善や薬物療法が行われますが、重度の場合は血管拡張術やバイパス手術などの外科的治療が必要となることもあります。
閉塞性動脈硬化症は、早期発見と適切な治療が非常に重要です。脚の痛みやしびれを感じた場合は、お早めにご相談ください。
肺血栓症・深部静脈血栓症
深部静脈血栓症は、足の静脈に血栓が形成される疾患で、特に片側の足にむくみや痛みが現れることがあります。血栓ができた場合、血流が妨げられ、放置するとその血栓が肺動脈に移動し、肺塞栓症を引き起こす可能性があります。これは、血栓が肺の血管を詰まらせることで発生し、命に関わる緊急事態です。
当クリニックでは、深部静脈血栓症や肺塞栓症の診断には超音波検査や心電図、血栓マーカーのDダイマー測定を用います。治療には抗凝固療法(血液をサラサラにする薬物)が一般的ですが、病態に応じて入院加療が必要となるために経験の豊富な連携医療機関に紹介いたします。
よくある症状
息切れ
息切れを引き起こす可能性のある病気としては、狭心症や心不全を含む循環器の障害、気管支喘息や肺炎、肺気腫などの呼吸器の問題、貧血や甲状腺機能障害などがあげられます。これらのように、息切れの原因は多岐にわたりますので気軽にご相談ください。
循環器の問題
呼吸器の問題
- 気管支喘息
- 気胸
- COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)
- 肺炎
- 間質性肺炎
その他の身体疾患
- 貧血
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- 腎不全など
- 過換気症候群に代表されるストレスやメンタルの問題による自律神経失調症
動悸
心臓が通常以上に速く、または強く拍動することで感じる胸のドキドキやバクバクする状態です。脈が飛ぶような脈の欠落として感じる場合もあり、息苦しさを伴うことがあります。
また、アップルウォッチに代表されるスマートウォッチに搭載された心拍数モニタプログラムなどで通知を受けた場合はデータを印刷してお持ちいただければ診療に役立てますが、通知はあくまで参考情報であり、正確な診断ではありません。
当院では心電図検査に加え、24時間ホルター心電図など専門的な検査を実施して診断を行います。
原因となる疾患
- 心房細動
- 期外収縮(心室性、上室性)
- 発作性上室性頻拍
- 心室頻拍
- 貧血 ・甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- ストレスやメンタルの不調による自律神経失調症
倦怠感・疲れやすい
過労やストレス、睡眠不足によって引き起こされることが多いですが、循環器疾患に伴う循環不全や低酸素状態、徐脈性不整脈による心拍数の低下を倦怠感として感じることがあります。また、見落とされやすいのが甲状腺機能障害ですが、採血による評価が可能です。
体重の減少を伴う食欲の低下などは悪性腫瘍が隠れている場合もあり医師の診察が必要です。循環器疾患に限らず、必要があれば専門医療機関に紹介しますのでご相談ください。
原因となる疾患
浮腫み
体の皮下組織に余分な水分が蓄積する状態です。過剰な塩分摂取や長時間同じ姿勢を保つ習慣、加齢に伴う足の筋力低下や活動の低下などで起こりますが、尿量の減少や短期間での体重の増加や息切れなどを伴う場合、片側性の場合(多くは左側のみ)には腎不全や心不全、深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)を含む深刻な疾患が原因で起こっている場合がありますのですぐに医療機関を受診してください。
治療が必要となる疾患
心電図検査で異常を指摘された
心臓は電気の流れ、電気活動により収縮することによってポンプとして作用します。
心電図検査は体に装着した電極で心臓から発生する微弱な電気信号を捉えて収縮と拡張の変更を波形で表したものです。不整脈や心筋の損傷や変化は心電図変化として現れるので循環器領域においては基本的な検査ですが評価には専門的な知識が必要です。
健康診断での異常が重篤な疾患の早期発見につながることも少なくないので心電図異常を指摘された場合は症状がなくても過去に精密検査したことがなければ一度受診をしてください。
心雑音を指摘された
健康診断で心雑音を指摘された場合は放置せずにご相談ください。
当院では聴診により原因や重症度を推測し、心エコー検査によって原因を検索します。
病的ではない雑音であることもありますが、心臓弁膜症や肥大型心筋症、小児期に指摘できなかった先天性心疾患など治療や定期観察が必要な病態が見つかる場合があります。